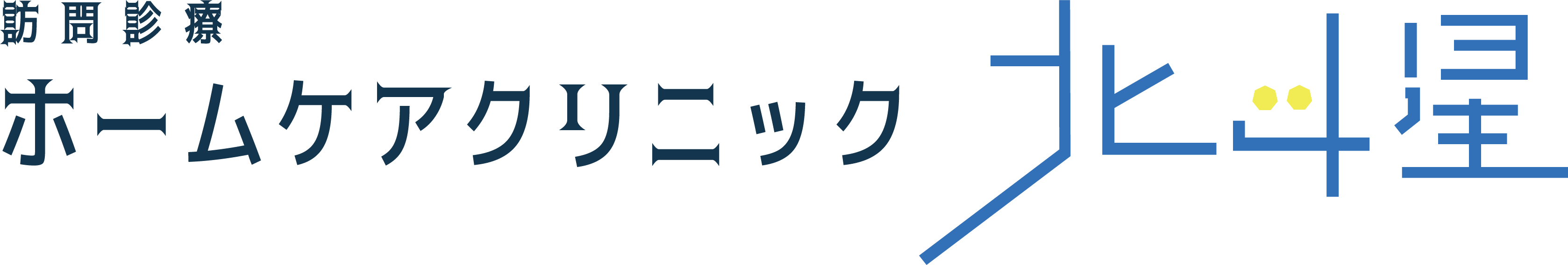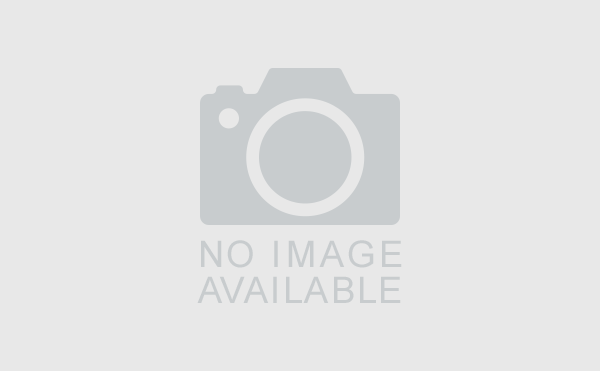僕らも桜を目指しませんか?
2019 男性81.41歳 女性87.45歳 / 1990 男性75.90歳 女性81.92歳
上記は2019年と、その約30年前の1990年の日本人の平均寿命である。この30年で日本人の平均寿命は一段と伸びた。思い返せば母方の祖母とその兄弟姉妹は35年くらい前に大方亡くなったが、皆さん70〜75歳くらいだったと記憶している。父方の祖父も同じ頃に88歳で亡くなったが、大往生だねと当時は皆で感心したものである。現在、当院をご利用いただいている患者さんの平均年齢は、恐らく男性85歳、女性は90歳を超えている。90歳近くになると流石に通院が難しくなり、訪問診療を利用される方が増え、当院の患者さんの年齢層が高くなるのだろう。当院の最高齢は106歳女性、今も車椅子自走されている。他100歳を迎えた患者さんは3人いらっしゃる(いずれも女性)。一方、健康寿命という言葉がある。健康寿命とは「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことであり、2019年時点で男性72.68歳、女性75.38歳である。健康寿命を延ばすこと、そして平均寿命と健康寿命の差を縮めることがより重要と言われている。なぜなら差が縮まることは健康に過ごせる期間が延びていることを意味しているからだ。
80代後半になると何かと体調を崩しがちとなる。超高齢者の疾患の代表格は感染症と心不全である。脱水傾向からくる尿路感染、嚥下機能低下に伴う誤嚥性肺炎、インフルエンザや新型コロナをこじらせて細菌性肺炎になる方が増える。また高齢の方は心機能が低下している場合が多く、感染症を契機に心不全を悪化させるケースが増える。独居だった高齢者が施設入所を機にそれまでの粗食から施設が提供する食事を摂るようになり、その結果塩分過多となって心不全が悪化するという皮肉なことも起こる。そして病気を繰り返す度に基礎体力が奪われ、臥せがちな生活となっていく。さらに食べる量はおろか口にする水分量も減り、いわゆる老衰という段階に突入する。
老衰が進み心配される家族も多いだろう。私は家族に以下のように説明している。「老衰は誰もが迎える宿命であり、食べる量が減るということは身体自体が食物を欲していないのである。飲食ができない場合、点滴をしてあげたくなるかもしれない。確かに生命力がある方が熱中症などの時は一時的に点滴が必要であり、生命力があれば点滴をしても身体中の細胞が全て消化してくれる。しかし生命力が落ちている場合、点滴をしても消化しきれず身体に残ってしまう『むくみ』と呼ばれる状態になる。治療するにも体力が必要で、治療に耐えうる体力が残っているかが重要なんです。植物も萎れて朽ちていくように、人間を含めた動物もむくませるより枯れるようにしてあげるほうが実は本人も楽なんです。僕らはこれを『枯死』と呼んでいます…」。以下は明治の思想家、岡倉天心の言葉である。
「花は人間のように臆病ではない。花によっては死を誇りとするものもある。日本の桜がそうで、彼らはいさぎよく風に身を任せるのである…」
僕らも桜を目指しませんか?