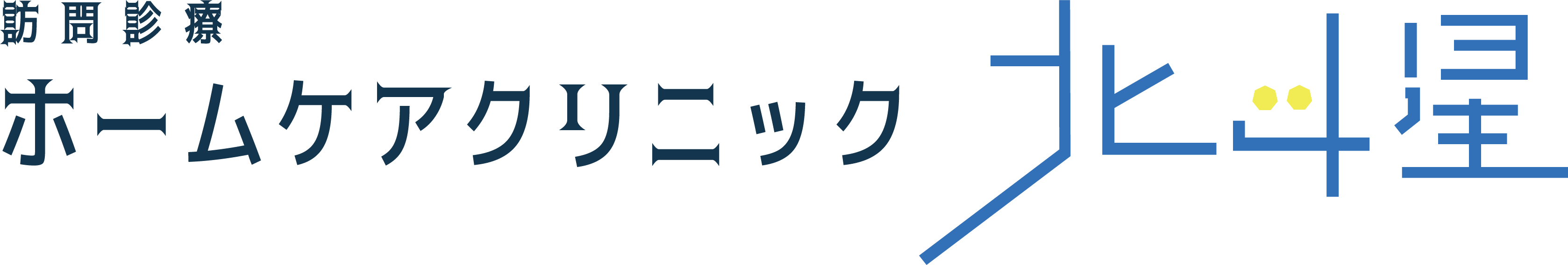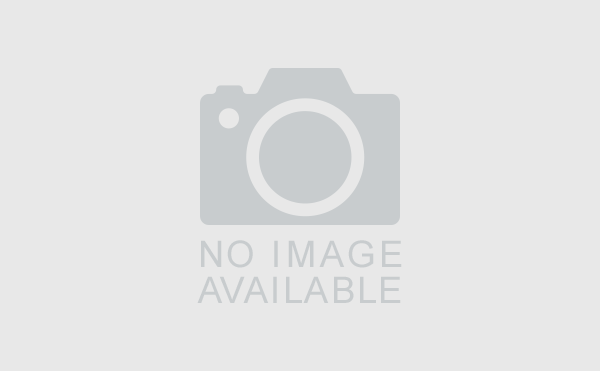地域包括ケアシステム
心筋梗塞や脳卒中患者を受け入れ、心臓手術も担うある地域の中核医療機関の先生と面談していた時のことである。「当院も今後は訪問診療に力を入れていかなくてはいけない」とおっしゃるので、「貴院がですか?」と訊き返した。「医療者もどんどん高齢化していく。これからは患者さんにはできるだけ家にいていただかなくてはいかんのだよ」とのご意見だった。
当院の患者さんの平均年齢も男性85歳、女性90歳を超えており、ご長寿社会であることをひしひしと感じる。90歳を超えてくる方は基本的に身体が丈夫なものの、さすがに寄る年波には抗えず、日ごと老衰が進まれている印象を持つ。「早くお迎えが来ないものか?」、「容体が悪くなっても何もしなくて良いから」とおっしゃる患者さんも多い。そういう方には、「分かりました。●●さんが祖父母を見送った時と同じようにさせていただきます」とお答えしている。お迎えが来た暁にはご自宅で、自然な形でお見送りをさせていただく、ひいては当院が目指しているのは昭和30年代までの医療の再現である。
現代の少子高齢社会を見据えて提唱されたものに「地域包括ケアシステム」がある。地域包括ケアシステムを厚生労働省的にまとめると、
・団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供されるシステム
・認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためのシステム
・高齢化の進展状況には大きな地域差がある。地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステム作りを市町村や都道府県が担う
まずは少子高齢化への対策、例えば生産人口を増やすための施策などが必要だと思うのだが、このような素敵なシステムをどのように構築していけば良いのか、保健、医療、福祉関係者に聴き取り調査をしたことがある。調査の結果、システムの構築には「2種類の会議の設定」、「良好なコミュニケーションの構築」、「コーディネーターやリーダーの存在」の3つの要素が必要であること、そしてこれらはチームを形成し、チームを発展させるのに必要な要素であることが示唆された。つまり、地域包括ケアシステムとはチーム作りに他ならないのではないか。当院も2年前、南渡島地区の地域包括ケアシステムに仲間入りさせていただいた。頭の中では分かっているつもりだが、当院もチームの一員として地域包括ケアシステムに貢献できているだろうか。そして、一緒に働いていただく他事業所の皆様にそのように評価していただけているかといえばまだまだだろう。他事業所の皆様に利用していただきやすいクリニックにしていく、開院3年目を迎える当院の今後の課題である…
(保健、医療、福祉関係者への聴き取り調査をまとめたもの)
(上記拙著を加筆修正して和訳したもの)