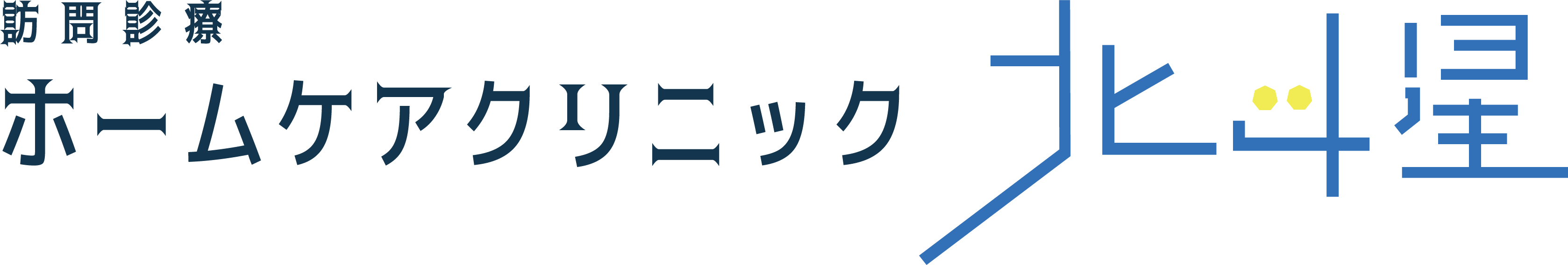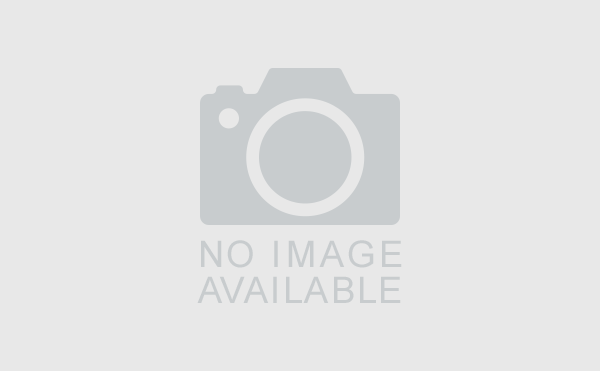病いの語り
私が「物語」に興味を持つきっかけは、医学科初学生の頃に読んだ『病いの語り』という本だった。著者はアーサー・クラインマンというアメリカの精神科医で、医療人類学という分野の研究者でもある。さて、我々は「患う」ことを表現する時、『病い』、『疾患』、『病気』と複数の言葉を無意識に使っている。小難しい話をして恐縮だが、本題に入る前にこの使い分けを本書の言葉を借りて説明したい。クラインマンは本書の中で、「患う」という経験の型はどこにでも見られるが、その患うことが何を意味し、その経験をどのように生き、その経験にどのように対処し扱うかは、実にさまざまであると語る。つまり、患うという経験の「型」を純粋に生物医学的に突き詰めたものが『疾患』であり、患者を取り巻く様々な患う「経験」を掘り下げようとする時に用いるのが『病い』である。そして今日の医療ケアシステムは生物医学的に大きく発展したが、医療者の注意が病いの経験から遠ざけられ、治療者は人を癒す技術の中でも最も古く、最も力を持ち、最も実りのある側面を放棄してしまっていると指摘する。本書の目的は、具体的な事例を出しながら慢性の病いをもつ患者をケアするための手引きを示すことにある。
38歳、ユダヤ系で独身の白人男性が15年間続く腹痛に悩まされている。腹痛が始まったのは大学院で博士論文に取り組んでいたころ、身体医学的検査でははっきりした原因は分からなかった。この腹痛のため博士論文はとん挫し、就労もままならず、失業と転職を繰り返し現在の低賃金の事務職を得た。学問的業績がなく、低い地位の仕事に甘んじていることへの自己嫌悪に苛まれながら暮らしているが、クラインマンはこの慢性腹痛について以下のように解釈している。彼の博士論文のテーマはある地域のナチス党員に関するものだった。彼は一人のユダヤ人として、この地方のナチス党員がどのような役割を果たしたのか明らかにしようとした。しかし、地元住民にすると自分たちの歴史の暗部を掘り返されることになる。地元住民の協力を得られないばかりか妨害にも逢い、彼は博士論文をとん挫せざるを得なかった。ユダヤ人が家畜用貨車に詰め込まれ絶滅収容所に送られるのを、なすがまま傍観し何もしようとしなかった人々が抱いた存在論的な罪悪感を彼も抱いていた。そして、同胞の大虐殺という巨大な真実のささやかな一部分を追求しようとしてなしえなかった自分を罪深い調査者と表現した。倫理的証人になれなかったと語る彼の話を傾聴しながら、クラインマンはある光景を追体験していた。旅行中、クラインマンは激しい雨に見舞われ、とある共同墓地に雨宿りした。それはあるユダヤ人一家の共同墓地だった。生年月日の違いから11名の家族関係は判るのだが、命日が全員同じ日であることに気づき、ユダヤ人であるクラインマンは光輝く墓石の表面を貫いて、その暗黒の内部を見る想いをしたのである。クラインマンはこの事例に「生きることの痛み」とタイトルをつけ、以下のように締めくくっている。「慢性の病いをもつ患者のなかには、苦痛や患うことが、生物学的疾患過程よりも、その人の人生に(中略)より関わっているという人がいる。治療者や家族は、人間の不幸を研究する歴史家と同じように、(中略)症状のなかや、病いの背後に、その嘆き叫ぶ声が聞こえるようにならなくてはいけないのかもしれない」(p112)
当時、出入りしていた教室の教授の本棚にも本書が置かれていた。「我々は患者の話をどこまで聴けば良いのでしょうか?」と教授に尋ねた。教授は「とことん聴くしかないのではないでしょうか」と答え、医者というのは大変な職業だなと感じたものだった。私にも同様の経験がある。当直をしていた時、精神科の病棟から診察依頼があった。50代前半の女性、主訴は嘔吐と便秘だった。その後も嘔吐と便秘は続き、主治医の精神科医から内科併診を依頼された。検査をしても特に異常は見当たらず、絶食輸液管理を経て流動食から徐々に摂取できるようになった。お粥まで食べられるようになり併診を解くのだが、嘔吐と便秘が再燃し主治医からコンサルトされることを繰り返した。『なぜ食べられなくなるんだろう』と悶々としながら4回目の併診となったある日、彼女から「先生、お話があるの」と言われた。用件を訊ねると、「私、元の(精神科)病院に戻りたくないの。ここに置いといてもらえないかしら?」と言われた。『そういうことか…』と合点がいき、「ごめんね。僕は内科的にコンサルトされているだけで、貴方の主治医ではないからご相談には乗ってあげられないんだよね。主治医の先生にはお話しておくけどね…」と返事をするしかなかった。